 |
 |
峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2025 > 桃川峠・村上
 |
 |
2025年7月5日(土)
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
●Youtube 動画 桃川峠のダウンヒル |
 |
 |
|
イヨボヤ会館 昭和62年4月にオープンしたこの施設、日本最初の鮭の博物館だそうだ。 |
 |
 |
|
|
 |
|
「千年鮭きっかわ 井筒屋」故郷のいのちを伝える鮭料理
鮭のまち、新潟県村上市初の鮭料理専門店だ。 |
 |
 |
|
|
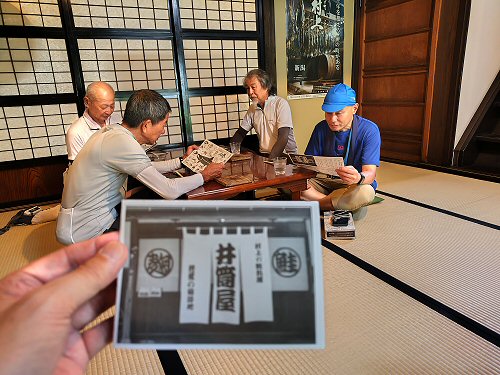 |
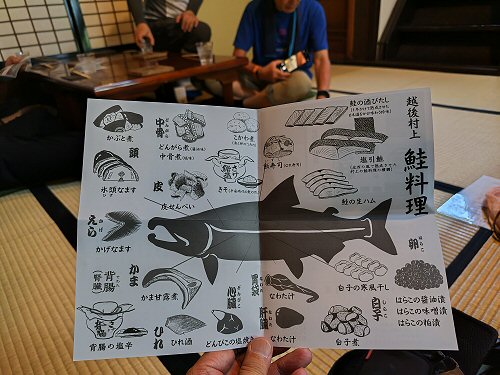 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
千年鮭とは
塩引き鮭とは
天井の梁から吊り下がっている鮭の姿に圧倒される。 |
 |
|
|
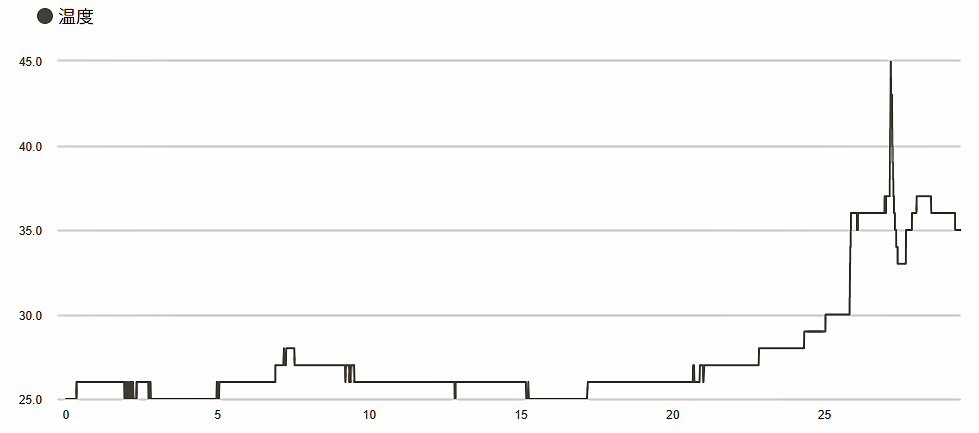 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
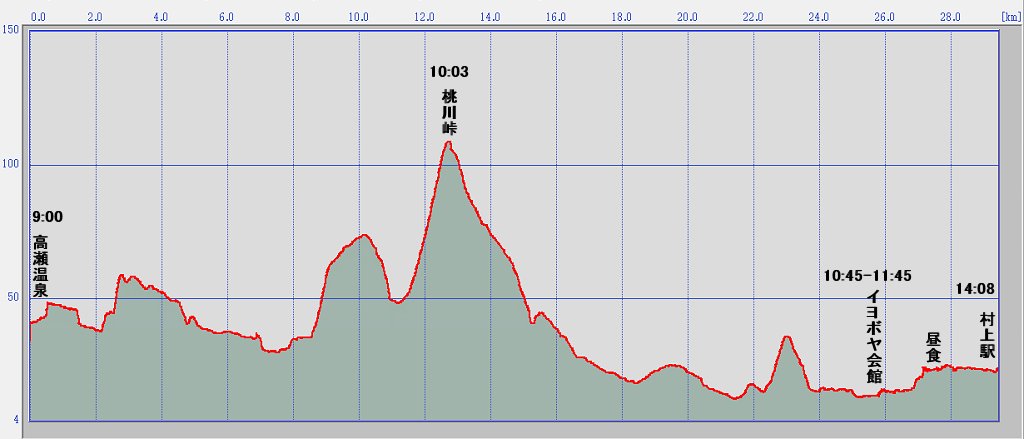 |
| 距離:
29.4 km 所要時間: 5 時間 08 分 41 秒 平均速度: 毎時 5.7 km |
最小標高:
13 m 最大標高: 108 m |
累積標高(登り): 174 m 累積標高(下り): 191 m |
(2025/7/5 走行)
峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2025 > 桃川峠・村上