 |
 |
峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2006 > 樽見鉄道・温見峠
 |
 |
2006年9月8日(金)
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
根尾谷淡墨桜 凄い巨木である。柵で囲われ、多くの支柱で支えられて保護されている。 |
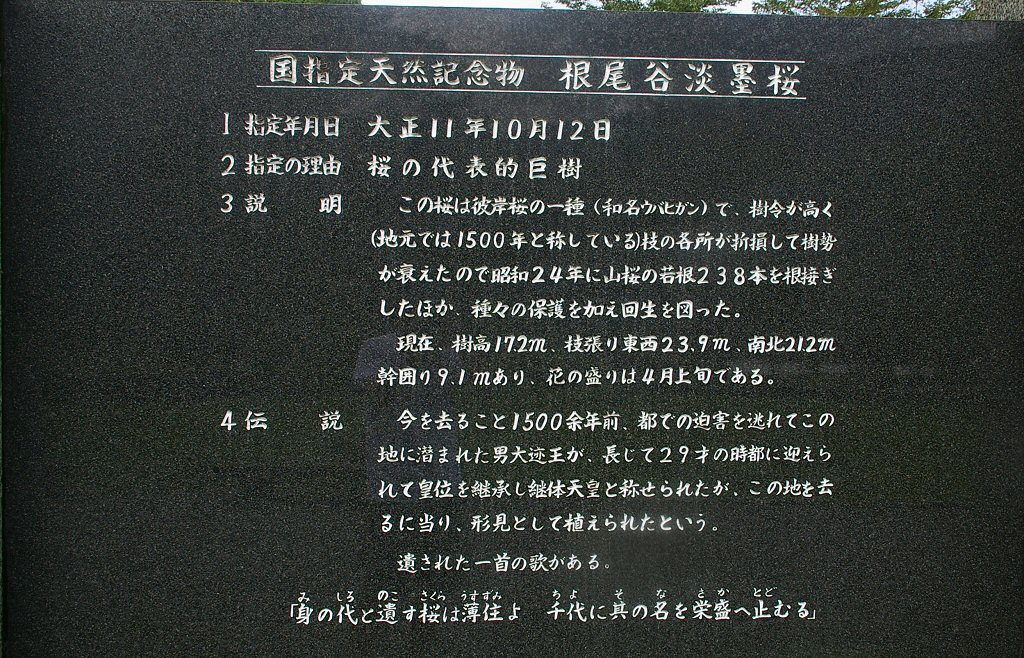 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
こんなすごい断層付近に今いるのかと驚いた。 巨大な断層の模型が物凄い。地層はこんな風になっているのかとよくわかる。
根尾谷断層 学習コーナーでは、根尾谷の自然を学ぶことができる。 |
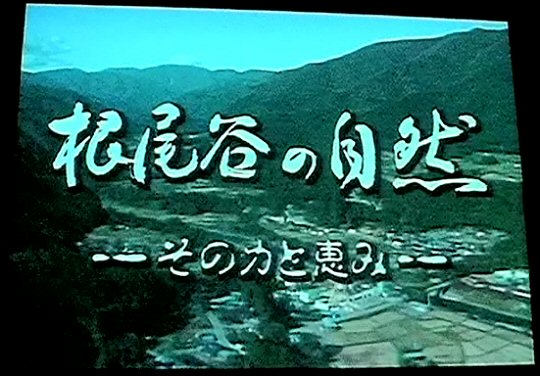 |
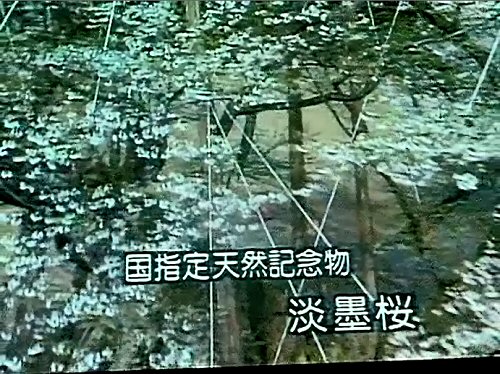 |
|
|
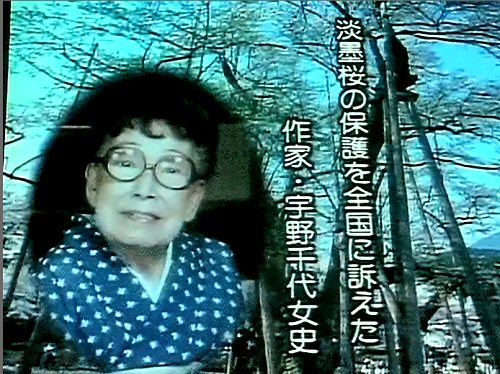 |
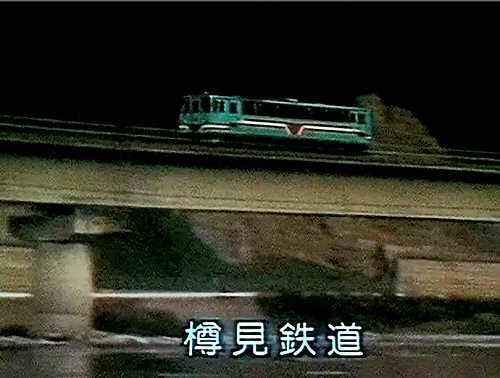 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
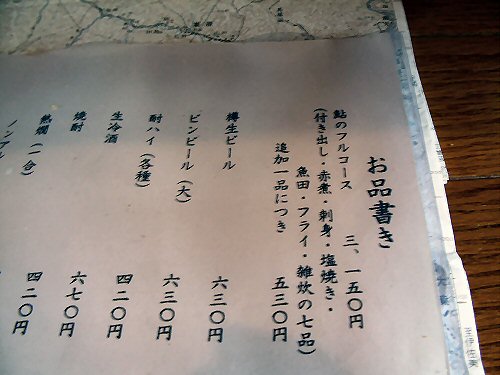 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
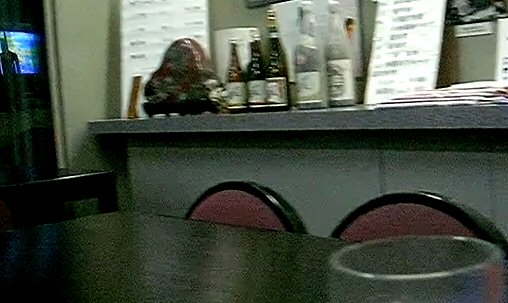 |
 |
| 距離:
30.3 km 所要時間: 6 時間 0 分 0 秒 平均速度: 毎時 5.0 km |
最小標高:
21 m 最大標高: 198 m |
累積標高(登り): 97 m 累積標高(下り): 241 m |
(2006/9/8 走行)
越美国境への憧れ
|
そしてニューサイ280 山本氏によるその後のレポートも見事な作品だ。 |
|
|
|
2006年9月9日(土) 温見峠 通行止め
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
旅の終わりに
|
|
 |
|
|
 |
(2006/9/9 走行)
「淡墨の桜 愛蔵版」 著宇野千代 平成8年 海竜社
|
紹介サイトより |
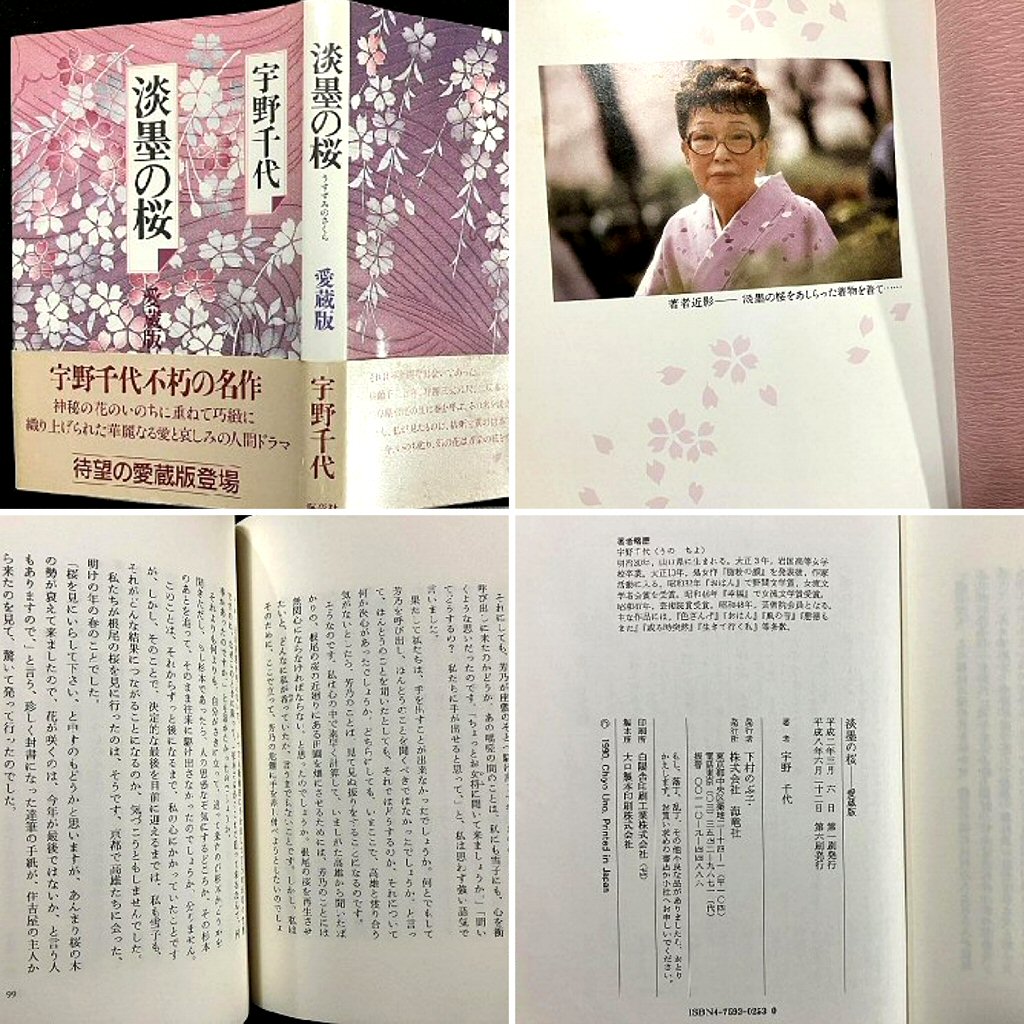 |
峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2006 > 樽見鉄道・温見峠